以前からネットでおつきあいのあるトロ・ツァキさん(@snoowbaall)さんがZINEをだされたので購入し拝読。
https://twitter.com/snoowbaall/status/1241355658789662720?s=20
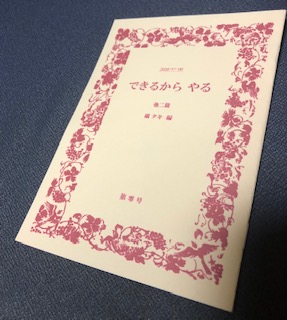
トロさん(と当ブログ主はお呼びしているが)のブログにしてもtwitterにしてもすっきりと洗練されたセンスで熱さとそこはかとなく漂うユーモアが心地よく(音楽のセンスも洒落てらっしゃるのよね)、喜び勇んで申し込んだのである。まず冒頭に読み途中だった、ナオミ・オルダーマン『パワー』に影響を受けたと書いてあってびっくり。シンクロ感が嬉しい。ストレートなメッセージの「できるからやる」、SNS時代のちょい前のネット文化をつづった「ミクシィ」音楽文化に造詣の深いトロさんならではの考察が光る「低空ダンス」(低空ダンスと農耕文化)どれも楽しいが、特に「ミクシィ」は貴重な時代記録だと思う(特にミクシィを経験していない当ブログ主には)。
2020年3月に読んだ本
コロナで世界中が混迷状況にあり、個人的にもいろんな問題が生じつつあり今後への懸念も多いのだが・・・それはさておき。
「ナイトランドクォータリーvol.17ケルト幻想」
怪奇、幻想、ほら話と国内外の幅広い短編が載り、井村君江インタビューはじめ、文学関連、そして映像作品や音楽にゲームまで網羅された論考やエッセイが並び充実した特集だった。
『イヴの末裔たちの明日』松崎有理
一部短編を読むだけだったが面白かった。「未来への脱獄」のようなSFミステリ、数学や暗号に取り憑かれた人々を描き思わぬ展開をみせる「ひとを惹きつけてやまないもの」、時代もの風ファンタジー「まごうかたなき」など粒揃いの短編集。幅広い読者にオススメ。
『茶匠と探偵』アリエット・ド・ボダール
東アジア化した未来の宇宙(しかもかなり奇想寄り)というユニークなアイディアのオムニバスSF。とはいえ全体のトーンはユーモアを基調とせず、抑え目でシリアスというそこもまた独特。個人的にはこうした発想に至った作家へ興味が向きつつも、作品自体はもう一つ波長が合わなかった。とはいえ宇宙船を出産する「船を造る者たち」とかなんだかすごい。
女性に対する抑圧をテーマにした近年の話題作を遅ればせながら読んだ。ある意味対照的な作品。
『パワー』ナオミ・オルダーマン
『声の物語』クリスティーナ・ダルチャー
『パワー』の方は電気的衝撃力を女性たちが持つようになり世界の様相が変わるという小説で、スーパーヒーローもののコミックやゾンビなどのシミュレーションものを裏返した形になっている。世界の変化にともない陰惨な出来事もおこるのだが、それを跳ね返すような活力に満ちたタイトル通りエネルギーに満ちた作品。
『声の物語」は保守的な価値観が反動的に支配するようになってしまったアメリカという設定で、前半『一九八四年』を思わせるじわじわと閉塞感が終盤に一転してストーリーが動き出す意外性が面白い。
どちらも今日的な問題を提起している傑作だった。
2020年2月に読んだ本
『息吹』テッド・チャン
前代未聞の<呼吸>SFのタイトル作をはじめ、期待通り傑作揃いだった。恒例の森下一仁さんのSFガイド、昨年ベストに挙げた。(24時まで投票できますよ!)
『病短編小説集』
「病」をテーマにした小説の歴史を短編で俯瞰できる丁寧なつくりのアンソロジー。「病」がいかに社会との関わりの中で規定されているのかが印象に残る。「黄色い壁紙」は別格として、「サナトリウム」「十九号室」が面白かった。
『冬至草』石黒達昌
これまで読んだ『新化』『人喰い病』と相通じる秀逸な科学的アイディアに加え、より奥行きがある作品が並び、素晴らしかった。画期的な医療技術が必ずしも世界を変えないところが著者らしい「希望ホヤ」、北海道という舞台が生かされたタイトル作、幻想風味の強い「月の・・・・」、あっと驚くSFミステリ「デ・ムーア事件」、死と病を見つめたシリアスな医療小説「目を閉じるまでの短い間」、研究不正というテーマを斬新な視点で描いた「アブサルティに関する評伝」とどれも傑作。もっと早く読んでおけばよかったな。
『コンパス・ローズ』アーシュラ・K・ル=グウィン
著者らしい粒ぞろいの短編集。基本的に駄作のない作家だという印象がより強まった。秀逸なアイディアの「アカシヤの種子に残された文章の書き手」「時間の欠乏という問題の解決法のいくつか」、性差別の残る現代日本そのままで背筋が寒くなるディストピア小説「ニュー・アトランティス」、作者らしくスタトレをパロっていて笑える「船内通話器」など素晴らしい作品が並ぶが、情景描写や普通小説「マルファ郡」の心理描写もまたいいんだよな。そして最後に南極探検を扱った「スール」を持ってくることによって、タイトルが、抑圧された女性たちの羅針図となろうとしていることがわかる。さすがである。
2020年1月に読んだ本、読書関係イベント
≪火星三部作≫ キム・スタンリー・ロビンスン
長い時間かかったが1月にようやく読了。あらゆる科学・社会学・人間学もろもろを総動員して、シミュレーションを行った大作。非常に難易度の高い創作法ではあるが、そうした手法自体は初期のSFにも存在している。しかし個人の博学的知識で書く時代(とはいえたとえばウェルズやヴェルヌには後進とは比較できない開拓者の困難さがあったろうが)にはない、膨大な情報を処理し統合する能力と胆力が必要と思われ、そういう意味ではとてつもない労作だといえる。読みどころは科学的データに基づきながら、イマジネーション豊かな情景描写で、思いつくだけでも軌道エレベーターの崩壊や大洪水や飛翔シーンなどなど、実にスケールが大きく美しい。全体のトーンはシリアスでやや重い感じなのは、読み進むのに正直苦労したが、歴史に残る作品であるのは間違いない。
『アメリカーナ』 チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ
現代のナイジェリアの社会が、アメリカや英国との関わりを含め、よくわかる小説。大部で登場人物も多く、どうしてもインテリ系の人々が中心になる部分がところどころ気になるか、基本骨格はメロドラマで、親しみやすい内容となっている。※追記 そういえば出てくる音楽ネタは雑学的に面白かったな。どういうポピュラー音楽があってどういうアメリカの曲が好まれたりしているかとか。
『マシーンズ・メロディ パリが恋したハウス・ミュージック (マンガでわかるハウス・ミュージックの歴史)』
ダヴィッド・ブロ&マティアス・クザン
日本では2014年に出版されたハウス・ミュージックの歴史を描いたバンドデシネの翻訳本で、2011年刊行されたものが底本。元々は2001年に1巻、2002年に2巻が出たものの合本という形式である。なので、基本的には1990年代末までの歴史が描かれている。基本ノンフィクションでフィクション部分をわかりやすくするために補足している構成。
全体を通じて、ハウス・ミュージックの歴史は単純に線的な流れになっておらず、いくつかの地域で時間がずれながら絡み合う複雑さがあり、なかなかわかりづらいのもやむを得なかったのかなあというのがまず第一の印象。そうはいってもポピュラー音楽の中でも、際物扱いされがちだったディスコ音楽が、その歴史をシリアスに振り返る視点がようやく得られるようになった事を裏付ける内容で、非常に意義深い一冊である。またやや込み入った歴史を基本的によく整理して伝えてくれることも、それほど詳しくない読者としてはありがたい。
フィクション部分の挿入については評価が難しい面もある。ドラッグを擬人化したパートや9章や10章の90年代の状況をつづったパートに関してはコミックならではフィクションならではの特性が生かされているが、5章のデトロイト・テクノ創生に関しては疑問が残る。基本的に実在のDJや証言者、曲を羅列している中で、5章はかなり史実を反映しているようだが本名が使われていない。これは他の部分を対比させるため、と解説にはあるが、うがった見方かもしれないが、現役の人々である重要人物たちと事実関係でもめないように配慮したのではないかではないかと疑う。少々浮き上がったパートだ。
残念ながら2002年に亡くなった作画のマティアス・クザンはヴェトナム系であることが記されているように、このハウス・ミュージックは多様な人種、地域の文化が混淆しており、一見温かみがないあるいは個性がないと批判されがちなデジタル・ミュージックにそんな要素があるところが非常に面白い。
ちなみにジェシー・サンダースについて、記載はあるものの「女に集中しすぎ」とやや辛辣な評価を受けている。
『黒き微睡みの囚人』ラヴィ・ティドハー
ナチスを題材にした改変歴史ものは数々あるが、ヒトラーを私立探偵に据えるというアイディアはかなり意表をつくものだろう。一見思いつきだけのように見えるこのアイディアだが、社会から疎外され、個人の価値観で行動する人物という点やフォーミュラフィクションの演出含め意外にも私立探偵がフィットしている。著者はイスラエル生まれで、全体に枠物語を配することによって、荒唐無稽な設定という印象とは異なる多層的な奥行きを作品に持たせることにも成功している。年間ベスト級の傑作。オズワルド・モズレーなどについても本作で知ることができたのもよかった。
『偶然世界』フィリップ・K・ディック
くじで支配者が決まり、短時間で交代してしまい、退くと命も狙われる世界。設定はかなり面白そうなのだが、開始早々設定が緊迫感なくゆるくなり、登場人物たちやエピソードの交通整理もあまりうまくいかずまとまりが今一つの長編第一作という感じ。ただところどころスリリングなシーンもあったりしてそこここにディックらしさは見える。それにしても長年ディックに親しんでいるので、傑作ではなくても妙に安心感をもって読んでいることにも気づいた。読み途中のル・グィン『コンパス・ローズ』も同じ感じがしている。長いつきあいの友人といるみたいなんだよね。
というわけで丸屋九兵衛さんの新イベントブッカー・T・ワセダ第1回に参加。記念すべき第1回は丸屋さんが最も愛するというアーシュラ・K・ル・グィン、ということでスタトレに続いてもちろんこちらも参加。丸屋さんの深いル・グィン愛、そしてル・グィンの切れ味鋭い名言の数々に感服しつつ、前回のhttp://funkenstein.hatenablog.com/entry/2018/07/01/213053=追悼トークよりも短編への言及が多く、短編好きのブログ主としては嬉しかった。名作「オメラスから歩み去る人々」(『風の十二方位』)はもちろん、ユーモアのセンスが光る「アカシヤの種子に残された文章の書き手」「船内通話器」(現在読み途中『コンパス・ローズ』)、見当たらないので購入し直さなきゃ『内海の漁師』、男性原理の支配する社会への強烈なる皮肉「セグリの事情」(『世界の誕生日』)、『言の葉の樹』、性別関係が複雑な世界を描いた「ワイルド・ガールズ」(最近手放したので買い直すことにしたSFマガジン2004年3月号収録)・・・。文化人類学の記録形式で記述された野心的な『オールウェイズ・カミングホーム』は異常な古書値になってしまって後悔しつつ、もっとル・グィンを読みたくなった。
2020年1月に観た映画、イベント
「マイマイ新子と千年の魔法」(2009年)
録画視聴。「この世界の片隅に」の片渕須直監督の、日常と非日常が重なる世界を巧みに描出する手腕がよくあらわれていて面白かった。
「劇場版 天元突破グレンラガン 紅蓮篇」「螺巌篇」(2008、2009年)
録画視聴。タイトルは知っていたものの予備知識ゼロで観たが、楽しい作品だ。ドリル、といえば世代的には破裏拳ポリーマーのポリマードリルあたりを思い浮かべ、そういえばドリルには胸躍る何かがあったなーという記憶がよみがえる(「あのぶっといドリルがいいんだ!」といっていたどちらかというとオタク方面ではなくひょうきんものポジションだったウエダくんは今何をしているだろうか)。そのドリルが世界の命運を握るといった感じの大仰で明るいカラーが全体にあるところが楽しい。さらに「螺巌篇」になると宇宙が舞台になり、地面を掘るドリルが宇宙へ!?といった不安感を他所に、次元を穿つといったさらに大風呂敷が広げられる展開には腹を抱えた。こういうのは好きです。
「スタートレックBEYOND」(2016)
録画視聴。ファーストシリーズの賑やかなノリを再現しつつ、登場人物たちの設定を現代的にブラッシュアップさせている。個人的には楽しめたが、このJ・J・エイブラムズの手堅さが鼻につくという人もまたいるんだろうなとは思った。
TVシリーズ「スタートレック:ディスカバリー」(2017-)
スーパードラマTVで15話まで終わったのでそこまで観た。後追いでTNGやDS9を観たので、本当の最近作を観たのは初めてで、いやすごいな現代作品はというのが第一印象(苦笑)。いやまあそれはともかく、登場人物の設定が見事にひっくり返されるなどそれぞれの立ち位置が鮮やかに入れ替わったりするところなど非常によくできてるなあと思った。続きも楽しみである。
さて丸屋九兵衛さんのスタトレイベントも参加してきたぞ。そういうわけでTNGやDS9を観てきたのでいろいろネタがわかって嬉しかった。ル・グインが賛辞を送ったピカードの兄とのエピソードはたしかに印象的だった。SF要素は皆無の回で、まだTNG数本しか観ていない時だったものの、しみじみさせるいい話だった。今から思うと、個人的にも最初のTOSとはちょっと違う魅力を感じさせてれるものだった。またファンの熱さ(クリンゴンに特化したイベントまであるとはね)、いろいろな出自の人が俳優陣に揃っていることもよく分かった。また全く知識のないVOYやENTについても知ることができた。
「パラサイト 半地下の家族」(2019)
久しぶりの劇場映画(なかなかいろいろ立て込んでてねえ)。ポン・ジュノ監督作品は何作か観ていて好きな監督だが、タイトルの地下のジメッとしたイメージをベースに、比較的平凡な人々の日常風景から巧みに仕掛けをほどこして、恐ろしい世界へ誘い込む。実は結婚無茶な話だったりするんだけど、そこはソン・ガンホら一家を演じる俳優陣に生活感があって、どことなくありそうとも思わせる。その結果、格差の問題をしっかりと際立たせてるのよね。流石。あととぼけたようなユーモアが漂うのもこの監督の味だ。ところで「殺人の追憶」をCSでやっていたのに気づいて終盤だけ観たんだが、地にどっしり足のついたようなところが魅力のソン・ガンホなんだけど、まだ若かったんだなあと思った(16年前だから当然か)。あとソン・ガンホ、ブログ主と全く同じ生年月日なんだよね。今更ながらこれもうれしい発見。